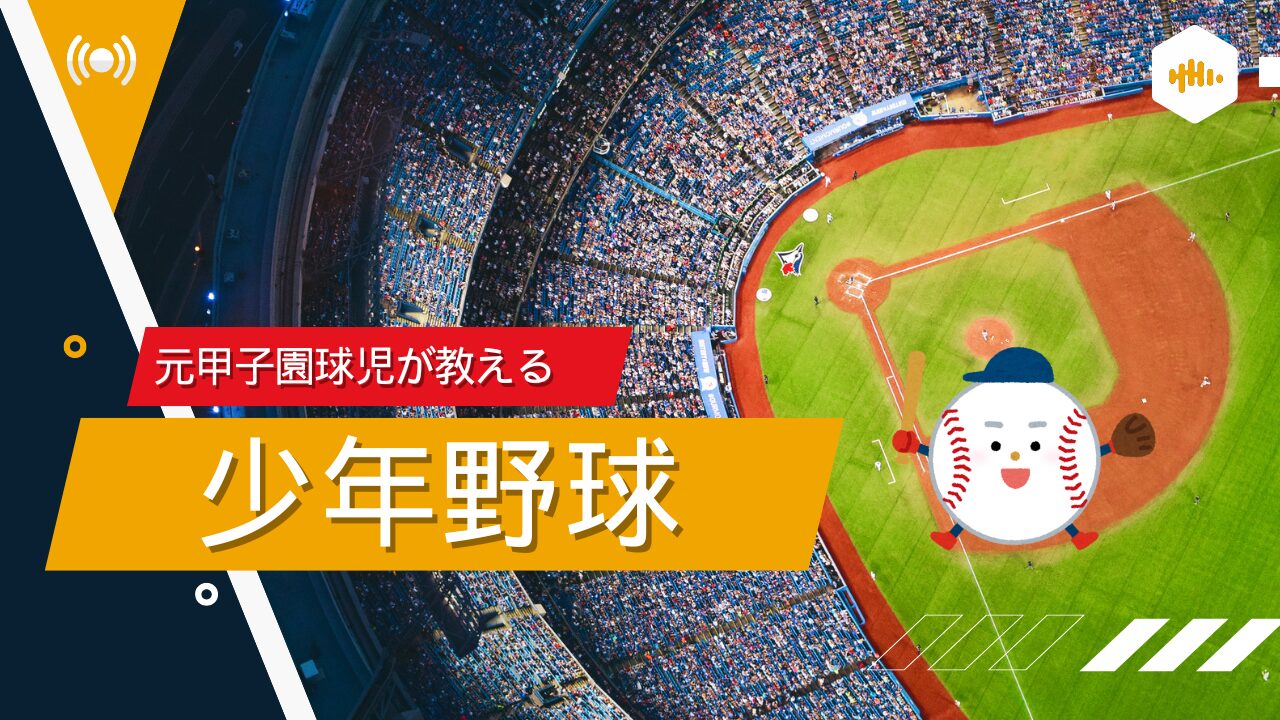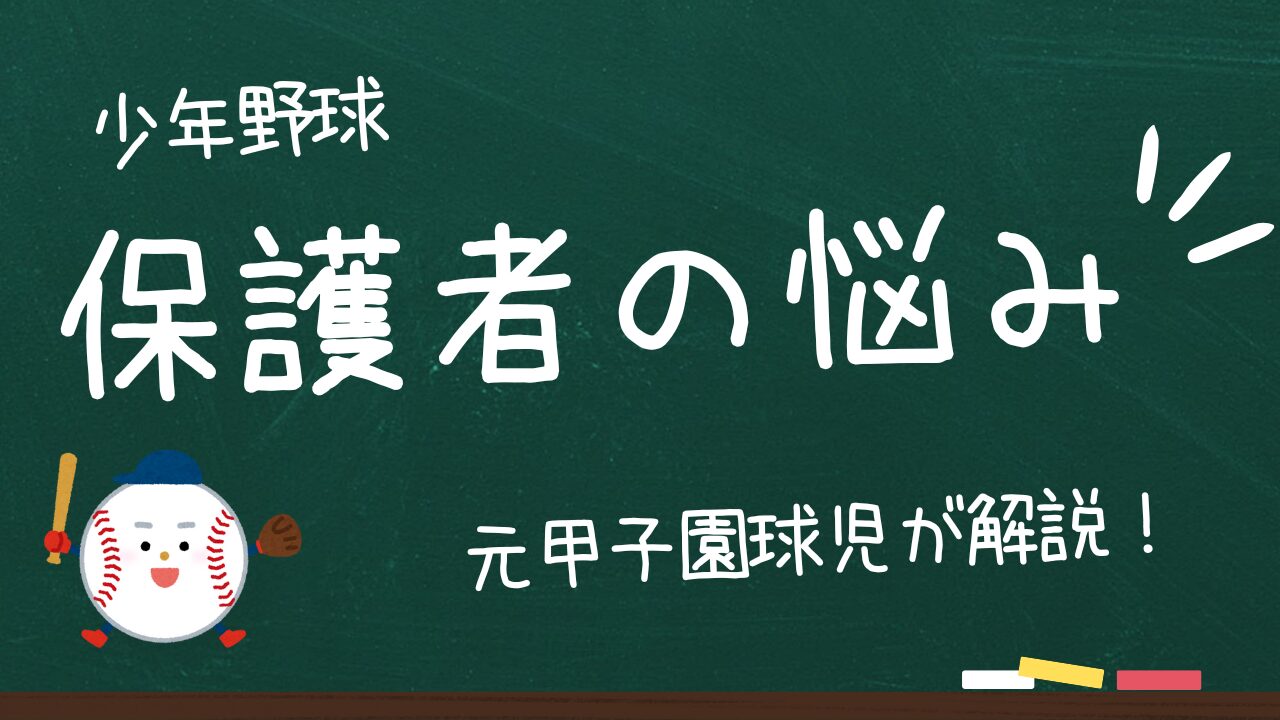広告
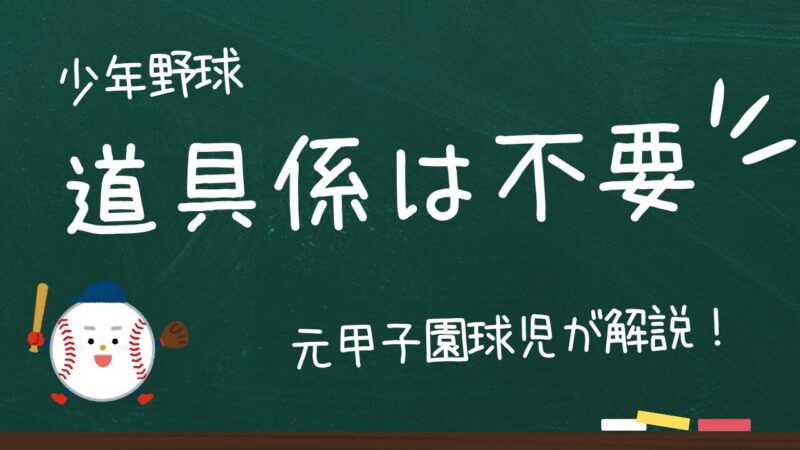
- 少年野球の道具係が苦痛
- 野球道具を保管するスペースがない
- 少年野球の保護者の負担を減らしたい
今回は、このような悩みについて解説します。
少年野球の保護者は、負担が大きいですよね。
その中でも、練習道具の保管でトラブルを抱えているチームが多いです。
自宅に保管するスペースを確保するのは大変ですからね。
しかし、トランクルームを使えば簡単に解決しますよ。
トラブルを放置しておけば、チームの雰囲気が悪いままです。
子供達が楽しい野球をできなくなってしまいます。
この記事を読めば、少年野球の保護者の負担を減らすことができますよ。
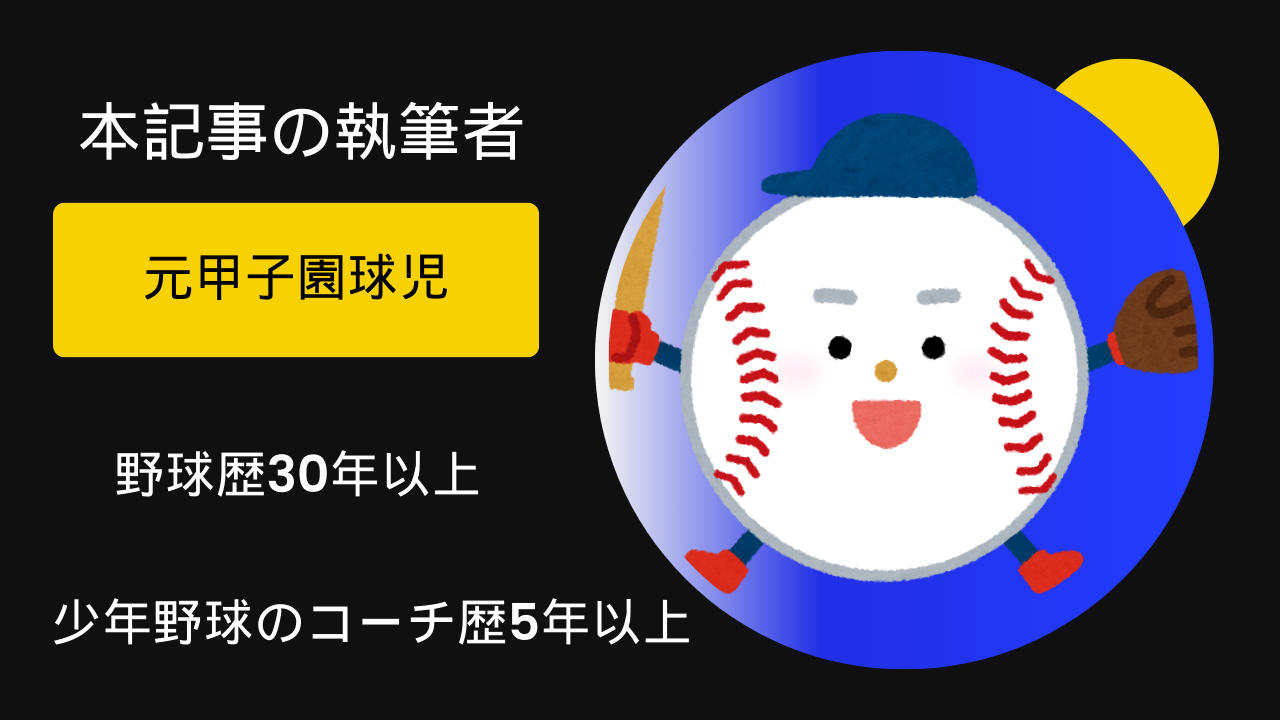
コンテナルームの申し込みはこちらから
【少年野球】荷物置き場におすすめのトランクルームとは?

トランクルームとは、収納スペースとして利用できるように設計された建築ユニットです。
頑丈な鉄製の構造で簡単に移動・設置できる利便性から、様々な分野で利用されるケースが増えています。
高い耐久性が最大の特徴で、道具や機材の安全な保管場所として最適です。
気密性が高いため、湿気や温度変化から荷物を守れます。
少年野球では、道具の収納や休憩スペースとして活用しているチームが多いです。
場所や大きさによってレンタル料が変わります。
レンタル料は、チームの会費で払えば大きな負担になりません。
暗証番号を共有すれば、誰でも開け閉めできます。
トランクルームの選び方
トランクルームを借りる際に検討することは、場所と価格です。
練習のホームグラウンドに近い場所が理想ですよね。
都会ほど価格が上がるので、価格とのバランスを考慮しましょう。
トランクルームは、大きさを選べます。
少年野球の場合は、小さなトランクルームで十分です。
トランクルームの価格
トランクルームを借りる際は、毎月のレンタル料の他に年払いの管理費が必要です。
地域によって様々ですので、事前に調べましょう。
| 大きさ | レンタル料/月 |
| 0.8帖 | 4千円 |
| 1.5帖 | 7千円 |
| 2帖 | 9千円 |
| 3帖 | 1万3千円 |
| 4帖 | 1万7千円 |
| 8帖 | 2万9千円 |
自分のチームでは1番安い「0.8帖、4千円/月」を借りています。
管理費は、年に2万円です。
道具のすべてを保管するのではなく、練習や大会で絶対に必要な物だけ保管するようにしています。
急な欠席にも対応できるようにするためです。
最低限の道具だけなら、軽自動車でも運搬ができますよ。
| 保管している道具 |
| 試合球 |
| 練習球 |
| レガース一式 |
| ヘルメット一式 |
| バット |
| スコアブック |
トランクルームのメリット
- 安全に保管できる
- 整理整頓しやすい
- コストパフォーマンスが高い
- 急な欠席にも対応できる
- 自主練習で道具を使える
安全に保管できる
施錠可能なため、盗難を防ぎ貴重な道具を安心して保管できます。
整理整頓しやすい
バットを壁掛け式のホルダーに掛けたりすることで道具の出し入れが簡単になり、練習や試合準備の時間を短縮できます。
コストパフォーマンスが高い
レンタルトランクルームは、固定の収納施設を建設するよりも初期費用が抑えられます。
耐久性が高いため、長期間にわたって使用できる点もコスト面での大きな利点です。
急な欠席にも対応できる
道具を持ち帰るシステムのチームは、道具係が急に欠席すると受け渡しが大変です。
自主練習で道具を使える
トランクルームで道具を保管すれば、チームの道具の自由に使うことができます。
ティーバッティングやベースを使った練習ができるのがメリットです。
トランクルームのデメリット
- 道具の管理が必要
- 固定費が掛かる
道具の管理が必要
誰でも道具を使える反面、紛失するリスクがあります。
私のチームは、使用後にチェックシートを記入する方法で対応していますよ。
固定費が掛かる
トランクルームをレンタルすれば、固定費が発生します。
持ち帰るシステムであれば、お金は掛かりません。
しかし、金額以上のメリットがありますよ。
- この章のまとめ
- トランクルームはコスパが高い
少年野球の保護者の負担を減らせる
【少年野球】トランクルームの口コミ
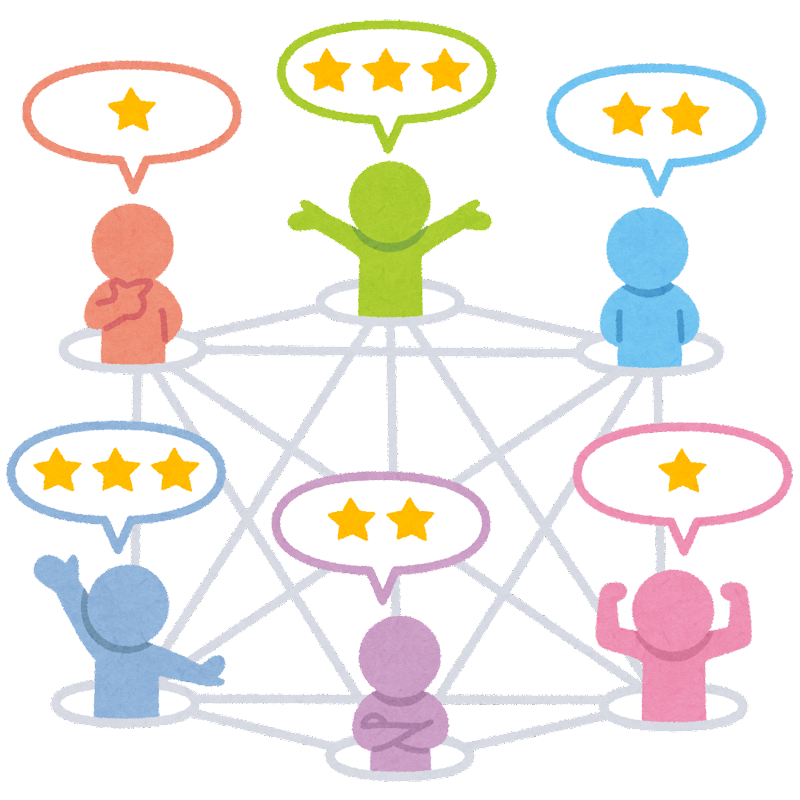

レンタルトランクルームを導入してから、道具の管理が格段に楽になりました。
以前は練習場に道具を運ぶ手間が大変でしたが、今は練習場の近くにあるので、そのまま使えます。
施錠できるので盗難の心配もなくなり、チーム全体のストレスが減りました。
月額費用も負担にならない範囲で、もっと早く取り入れればよかったと思います。

レンタルトランクルームを導入する際、費用が少し気になっていましたが、使い始めてみるとその価値を実感しました。
道具の管理がしっかりできるようになっただけでなく、雨天時に選手たちが待機できる場所としても役立っています。
保護者たちの負担も軽減され、全員から高評価です。
コストパフォーマンスは抜群だと思います。

複数のチームが使う共有スペースとしてレンタルトランクルームを活用しています。
各チームが自分たちの備品を収納できる区画を分けて使うことで、道具の混在を防ぎ、管理が非常に楽になりました。
耐久性が高く、安心して長期間利用できるのがいいですね。

僕たち選手にとっても、トランクルームができてすごく便利です。
練習や試合のときに道具をすぐに取り出せるし、前より整理されていて探すのが簡単になりました。
雨が降ったときも中で作戦会議をしたり、ちょっと休憩したりできるので助かっています。
僕たちの秘密基地みたいで気に入っています!

監督として、チームの運営を円滑にすることは重要な役割ですが、レンタルトランクルームのおかげで道具管理に関する悩みが一気に解消されました。
練習や試合のたびに道具を運び出す手間がなくなり、時間と労力を他の部分に使えるようになったのは大きいですね。
頑丈で施錠もできるため、安全面でも安心しています。
トランクルームは、チーム運営の効率化に欠かせない存在です。
【少年野球】道具の管理問題が発生する理由

- 野球道具は基本的に週末にしか使わない
- 道具を持ち帰ると車が汚れる
- 道具を持ち帰ると自宅に保管するスペースが必要
- いつも同じ人ばかり道具を持ち帰っている
- 道具を持っている人が急に来れなくなった場合に受け渡しが大変
- 道具の破損や紛失するリスクがある
これらの問題は、すべてトランクルームで解決します。
月に4000円でトラブルを回避できればいいですよね?
人間関係がこじれると、少年野球の楽しさが半減してしまいます。
- この章のまとめ
- 道具係はトラブルになりやすい
保護者のトラブルは子供に悪影響
【少年野球】実際にあった道具トラブル事例

私がコーチをしていたチームでは、決められた道具置き場がありませんでした。
道具係の人が自宅に持ち帰るシステムです。
実際は、車の大きさの関係で常に同じ人(Aさん)が持ち帰っていました。
他の道具係の人達の言い訳はこんな感じです。
- 軽自動車なので道具が載らない
- 家に保管するスペースがない
- 毎週来れるか分からない
やむを得ず、Aさんがいつも持ち帰ってくれている状況でした。
ある日、Aさんの子供が体調を崩して入院することになりました。
大きな大会の日で、Aさんが持っている道具がなければ試合はできません。
でも、Aさんが道具を試合会場に届けることは不可能です。
大会の棄権を考えましたが、他のチームの道具を借りて何とか試合ができました。
しかし、慣れない道具で試合をしたチームは初戦敗退です。
この一件で、トラブルが発生しました。
- 道具くらいAさんの家族が持ってこれなかったのか?
- 道具係の人達は無責任すぎる
- Aさんに任せすぎじゃないのか?
- もっと早く言ってくれれば取りに行ったのに・・・。
この意見を聞いたAさんは激怒しました。
それ以来、Aさんは道具の持ち帰りを拒否し、各家庭が分担して持ち帰るように変わりました。
急に欠席した場合は、道具を試合会場まで運ばなければいけません。
道具問題は、更に悪化しました。
チーム内の雰囲気も悪くなる一方です。
【少年野球】トランクルームの効果

トランクルームを借りてからは、道具管理に関するトラブルは一切なくなりました。
道具を取りに行ったり置きに行くのは当番制です。
全員で回すので、まったく負担になりません。
量も少ないので女性でも大丈夫です。
トランクルームの扉はダイヤル式なので、チーム員であれば自由に道具を使えます。
道具使用簿の記入を徹底し、道具の数量を管理するルールを決めました。
「トランクルームを借りて本当に良かった」という保護者の意見が大多数です。
- この章のまとめ
- コンテナルームは保護者に好評
【少年野球】トランクルームを活用して保護者の負担を減らそう
この記事では、少年野球の道具管理トラブル対策としてトランクルームについて紹介しました。
- トランクルームはコスパが高い
- 保護者の負担が減る
- 自宅の保管スペースが不要になる
- 道具係が欠席でも困らない
- 自主練でチームの用具を使える
少年野球のトラブルは本当に多いです。
トラブルが多いとチームの雰囲気が悪くなりますよね。
子供達にも影響します。
楽しく野球をやりたい子供達が可哀そうです。
心から野球を楽しむための環境を作ってあげるのが親の役目です。
トランクルームを活用してトラブルを解決しましょう。
コンテナルームの申し込みはこちらから
道具が紛失するリスクはありますが、在庫管理を徹底すれば対策可能です。
チームの雰囲気が良くなり、子供達にも大好評ですよ。